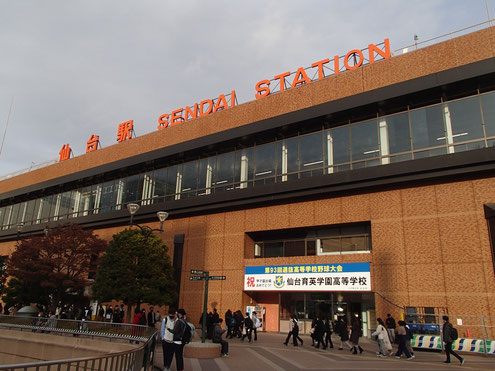八甲田山と青森の街
雪の八甲田山と青森の街を歩きに東北遠征してきました。

青森到着後、真っ先に訪れたのはここ青森市八甲田山雪中行軍遭難資料館。
約10年ぶりに来ることがで来ました。

入ってすぐのホールには、大惨事が判明する口火となった後藤伍長の銅像、これはFRP製のレプリカです。
本当の像は遭難の地となった八甲田北麓の馬立場に建っています。
雪の中に佇立したまま発見された往時の姿を映し出すような力強い像ですが、実際には行軍開始から4日後
(単に4日ではなく、地獄のような気象条件の中を飲まず食わず寝ずで歩きまわり、着の身着のままの夜を三晩越した後)
の発見であって、銃は持たず、手袋もなく、フードを深く被った姿で、自ら立っていたのではなく雪に腰まで埋没し倒れる事すらできなかった、というのが事実のようです。
とは言え210名(事後死も含め199名死亡)の遭難者のうち最後まで上官(神成大尉)に寄り添い最も帰営に近づいた後藤伍長の精神力は強靭であり、わずかでも早く遭難の事実を捜索隊に(自らの立ち姿で)伝えたという功績は大きいと思います。
そのわずかの差が救出された生存者の命を左右したかも知れません。
その生存者が後に現場での出来事や状況を話し、文字にし、それが今現在貴重な資料として伝っています。

資料館に隣接する幸畑陸軍墓地には遭難死者199名と生存者11名が埋葬されています。
写真は指揮官の山口鋠少佐と主任中隊長の神成大尉の墓標。
暗闇同然の一面白の世界で起きた遭難であり、生存者も少なく「何が起こったのか」「何が原因だったのか」が長い間謎とされ、事後の処理なども含め、一部憶測で書かれた文章や、ノンフィクションと見紛うフィクション作品(八甲田山死の彷徨:新田次郎(1971年)など)があたかも真実のように伝わってきた稀有な遭難事件であると言えます。
真実ではないことが一人歩きするということはよくあることかも知れませんが…
そんな中、ひとつ動かない真実は、210名の立派な体躯の軍人がひとつの気象遭難で199名死亡したということ。
この出来事には装備や情報が大幅に便利になったこの現代においても学ぶべき事柄がたくさん残されていると感じています。
有意義な見学を終えこの日は青森市内に前泊、明日の朝八甲田山に向かいます。

さて、登山開始。酸ヶ湯温泉のすぐ脇に夏道の登山口があり、そこからスタート。足回りはスノーシューです。
登り出しからいきなり急登!
ここには秋に来ていますが、全く面影なく…。
とは言いつつもMSRのライトニング アッセントにはちょうど良い勾配でした。

樹林の先に大岳が頭を出しました!
ここまではなだらかな樹林をトラバースしたり直登したり。
あんまり細かいルート取りは気にしないまでも、八甲田スキーマップに示された「大岳コース」をなるべく外れないように登っていきます。
自由なルート取りができるのは雪山の楽しさ、魅力のひとつですが、当然沢筋や上部の状態が見通せないような”雪崩の危険”があるところは避けます。
自由と責任は表裏一体です。
雪山でのシビアな判断は簡単ではありませんが、ちょっとした知識で雪崩地形を避けることは可能です。
自ら死地に入ることはしないよう行動に責任を持ちましょう。
その上で初めて自由は成り立つものだと思います。

正面に回ると…秋には大勢の登山者で賑わっていた避難小屋です。
とても同じ建物とは思えません。
メインの入り口にはとてもじゃないけど到達できず。
見えている窓からも入れる感じじゃありません。
大岳往復の前に小屋の風下で少し休憩。

酸ヶ湯に戻ってきましたー。
後半は気温が上がって雪がグズグズになり、暑くて参りました。
3月上旬の八甲田でこんな気候は意外でした。
この日は酸ヶ湯に一泊。
湯治棟に泊まりましたが、快適でした。

最後は ねぶたの家 ワ・ラッセ に寄りました。
これは 2021年青森ねぶた祭出陣予定 の特別なねぶた。
中止になった今年2020年に14名のねぶた師によって1体ずつ14体が作成された特別ねぶたです。

こちらは2019年の優秀制作者賞「瓊瓊杵尊と木花咲耶姫」です。
ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメ。秋に行った霧島神宮はこの二神が共に祭神でした。
神武天皇のひいおじいちゃんとひいおばあちゃんです。
有名なところだとコノハナサクヤヒメは富士山のご神体でもありますね。
それにしても ワ・ラッセ は初めて入りましたが、ねぶたがこんなに間近で見られる施設だとは知りませんでした。

これが2019年の最優先制作者賞(ねぶた大賞)の作品「紀朝雄の一首 千方を誅す」。
テーマは勉強不足でなんのことかわかりませんでしたが、舞う紙の表現が評価されての一等賞だったとのことです。
和歌を書いて鬼を退治するというような設定のお話のようです。

竹の骨組みのねぶたもありました。
現在の骨組みは針金が使われていますのでおどろくほど複雑な造形が可能ですが、昔は竹でしたので表現も変わってきます。
これは昭和30年に出陣したねぶたのリメイク作とのことです。
いまでもこれが夜の街に現れたらすごい迫力で異空間ですけど、当時はもっと夢のような空間のお祭りだったんでしょうね。
棟方志功記念館とここを続けてみることで、棟方志功がねぶたに強く影響されているということが少しわかったような気がしました。

こちらも優秀制作者賞の あおもり市民ねぶた実行委員会 「神武東征」。
色彩といい造形という"現代のねぶた"という感じの作品で物凄いの一言。
ねぶたの迫力に圧倒されたままワ・ラッセを後にしました。
これにて青森の旅は終了。
約10年ぶりの雪の八甲田、楽しいだけのいい山でした。
こんな日だけしか雪山に登ったことがないと「なんで昔とは言え八甲田で199人も死んだの?」ってなっちゃいますよね。
10年前は強風で視界も悪く、井戸岳付近から眼下に避難小屋(らしきもの)がちらっと見えはじめた時には「生きて帰れるな」と思った記憶があります(あの八甲田にいるという緊張感もあったのかな)。少し大げさですが、ほとんど白一色の時間が長かったので人工物の安心感はすごかった。
目指した山は同じですが、今回は全然違う山に登った印象です。
良い時だけ登っていられればこれほど楽で楽しいものはありませんが、一日の中でも天候変化がありますので…
まずは情報収集能力、それを活かす知識と計画力、更には自分の能力を良く知ること、そして当然相応の体力、技術。
やはり雪山はより総合的な能力が必要になりますよね。
情報収集の話で言うと、間違っても「冬の○○山は楽だった」「簡単だよ」などと言う自分の一時の体験だけで他人に気軽に勧めるのはやめた方がいいと感じます。
当然情報を受ける側も、ネットなどの記録を見て「簡単らしいよ」ではなく、厳しかった時の記事や敗退の記録なども併せて探して欲しいと思います。
情報過多な現在、山選びの方法も刻々と変わっているように感じます。
上手く使えば良薬、使い方を間違えれば毒。いまや情報の選別もひとつのスキルですね。
青森・八甲田には秋冬ときたので、次は花の時期に来たいです。あとはねぶた祭も!ぜひ今年は実施できるよう祈ってます。