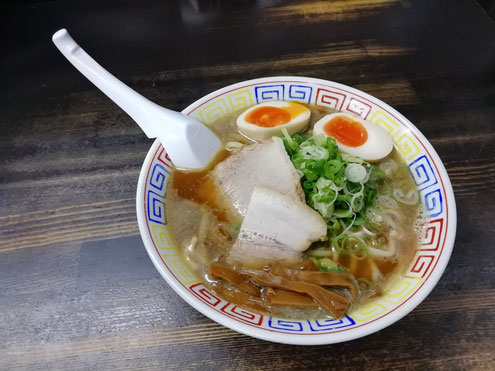ぶらり青森
八甲田山、十和田湖、奥入瀬渓流と青森県のドメジャー観光地を巡る1泊2日のゆるゆる旅に行ってきました。
day1

ロープウェー山頂公園駅から、歩き出し。
今日は赤倉岳、井戸岳、大岳を踏んで上毛無、上毛無を経て酸ヶ湯へ下ります。
どうやら紅葉も良いという情報ですし、なによりも無積雪期の八甲田は初めてですので楽しみです。

ロープウェー駅から田茂萢岳を踏んで赤倉岳の登りにかかると視界が開けました。
茶色い部分は田茂萢湿原で、左の小さな丘が田茂萢岳。
ロープウェー駅を基点にこの湿原と山を八の字回るコースが八甲田ゴードラインと呼ばれる散策路になっています。
左奥には岩木山も見えてます。

井戸岳は火口になっていました。
登山道はこの写真の左側の外輪山縁を進むのですが、冬に来た時はなんとなくですが、正面に見えている岩の向こう側をトラバースしたように思います。
強風と視界不良でとにかく尾根から離れないように稜線直下の深雪を延々トラバース&ラッセルした記憶があります。
欠けたエビのシッポが飛んできてバシバシ顔に当たって痛かった、そんな記憶も。

井戸岳から下ると鞍部避難小屋がありました。立派な建物です。こんなに嵩上げされた建物とは知りませんでした。
冬は当然の如くここに転がりこんで一息つきますが、今日は登山者が多く外で一休み。

このオオカメノキは芸術的な美しさでした。
重なり部分の濃い色が絶妙ですね。
奥の澄んだ黄色はオオバクロモジです。
個人の見解ですが、黄色に色づくものでは一番きれいな色だと思います。

最後は山地帯の植生に変わって、もう少し下るとあっさり酸ヶ湯に着いてしまいました。バスまで時間があったので、入浴。
いいとこ取りの八甲田山でしたが手軽でいいルートでした。
今日はここから十和田湖に移動して一泊です。
day2

一度は来たかった奥入瀬渓流。ここから約14kmの遊歩道が整備されています。
十和田湖は大きな河川の流入がなく濁ることが少ないので、流れ出る唯一の河川である奥入瀬渓流はとても水が澄んでいるのが特徴とのこと。

この水門で流量が一定に保たれるので氾濫せず、景観が保たれる…という話を目に耳にしましたが、実は違うらしい。
元々安定した水環境で、奥入瀬渓流の優れた景観は自然の力によるものとのこと。
全然関係ないですがこの水門のデザインがシンプルで格好いい。

奥入瀬渓流唯一の滝、銚子大滝です。別名は魚留の滝。
この滝があるので、昔は十和田湖には魚がいなかったようです。
和井内貞行(わいないさだゆき)という人が明治期に養殖事業に乗り出し、何度も何度も失敗を重ね、ラストチャンスとして試したヒメマスでいよいよ養殖に成功したとのこと。
今では『十和田湖ひめます』としてブランド化しています。

9kmほど歩き、石ヶ戸という休憩所のあるところまできました。
ここで渓流散策は切り上げてバスに乗りました。
なんというか、わいわい騒ぐ観光客が多くて、遊歩道と車道は隣接して車はすぐそばをビュンビュンだし。大量の路上駐車をパトカーがスピーカーで注意しながらうろうろしてるし…。
素晴らしい自然も景観も簡単に台無しにできます。
それのいい例。
そういえば今日は土曜日でした。せめて平日なら…残念。
バスで青森駅方面へ戻ります。

で、こちらが大型の掘立柱建物。
柱の径や底部にかかっていた土圧から複層だったのでは?と考えられて復元されていますが、壁があったのか?屋根があったのか?などは諸説あるので復元していないようです。
なんかモニュメント的なものかと思ってましたが、これが完成形ではないんですね。

こうやって復元されたムラを一望するとなんだか縄文の生活もけっこう楽しそう。
ただ、ここに550棟以上の竪穴建物があったらしいのですが、それだけ人がいれば現代人と同じような悩みなんかもあったのかも知れませんね。ご近所付き合いとか。
室内展示はいよいよ時間が無くてざっと見で終了です。また来ます。
それでは青森駅に戻ります。
急に思い立ってぶらりとやって来た青森の旅でした。「一度は行きたい」と思っていたところをピンポイントで回りました。
奥入瀬は観光地過ぎて少し残念でしたが、八甲田は十分ガイド対象になる山だと思いました。
実際にガイド登山の団体も何組かいたようです。
三内丸山遺跡をもっとじっくり見たいのと、あと八甲田雪中行軍の足跡を辿る旅もしてみたいのでまた再訪したいと思います。
無積雪期の岩木山も登らないと。
なんとなく当初の目的としてはガイド下見の感が強かったのですが、
訪れてみるとなぜか気の張りも消え失せて、だらっとした素晴らしい休暇になりました。
東北はどこの県も個性と魅力に溢れていて何度でも来たくなります。